
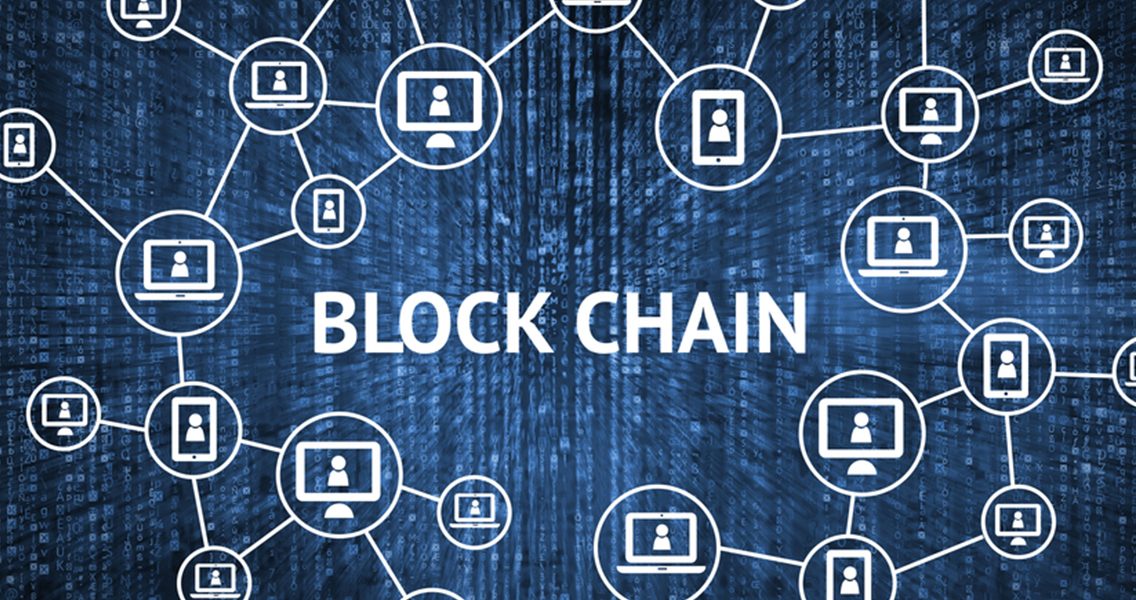
◇ブロックチェーンと今後の課題
仮想通貨業界では昨年を「膿を出した1年」、今年を「再スタート元年」と見る専門家もいるが、信頼されるブロックチェーン技術とは何か?を自問し続け世に公表してきたLibertyとしては、今後もブロックチェーンの問題に真摯に取り組む構えだ。そこで今回は今年の四半期を振り返り、仮想通貨を取り巻く脅威について特徴的な2つの事件を検証したい。
■マイニングに対するネガティブな憶測につけ込まれた「ETC51%攻撃事件」
マイニングとは「採掘する」という意味だが、仮想通貨について語る際には「新規の取引情報を解析しブロックチェーンを作成すること」との解釈が最も簡単だろう。情報解析をするには、当然ながら膨大な量の計算が必要となる。そこで、計算資源を採掘し提供できた人に対して報酬としてその通貨が与えられる仕組みが用意されている。これがマイニング人気を誘導し、我こそは!とこぞってマイナー達が採掘しようとするのに比例し、ハッシュレートも上昇した。マイニング人気とハッシュレート上昇という双方インフレ状態の産物として、マイニングプールが誕生した。
マイニングプールは、世界中のマイナーからの接続を受け皆のハッシュレートを集める「まとめ役」。巨大サーバーのようなものだ。これにより全体としてのハッシュレートはグンと上がり、ブロック発見率も格段に上り、サーバーとしての役割も高まった。また、ブロックチェーンに参加しブロックの承認を行なう機能も備えている。流れとしては、マイニングプールは承認が必要なブロックを見つけた際に、プールの参加者にハッシュ作成を要請し、参加者のうちの一人がハッシュを生成しブロック承認に成功すると、報酬は一旦プールのアドレスに送られる。その後、報酬は各参加者の作業量に応じて分配される。実にシンプルな流れだ。だが、マイニングプールの弱点は、マイナー達は通貨の価格が下落するとこれまたシンプルに撤退してしまう点だ。当然参加するマイナーが減ったマイニングプールでは監視する権力者数も減り、残った少ないマイナーのみに権力が与えられる。
さて、マイニングプールのこうした仕組みと裏事情にもし脅威的な何者かが気付いたらどうなるか?その恐怖を知らしめたのが今年1月の「51%攻撃」事件だ。今年1月、あるマイニングプールが「ETSの51%攻撃に成功した」と発表した。
「51%攻撃」とはその名の通り、マイニングにおいて半分以上を独占することにより攻撃者に都合良く取引を承認してしまう攻撃だ。マイナーが少ないのなら、脅威的な集団がその過半数を独占し自己都合的なブロック承認を続けたり監視権力を手中に収るのはいとも簡単である。たった10名の技術者で支えるサーバーをある日突然6名の技術者集団が乗っ取り「攻撃に成功した」などと世界に発表するようなものだ。作業量で発言権を得る仕組みであるならばその脅威は尚更だろう。この奇妙な発表に対してETC側はきちんと51%攻撃を否定したのに、「いや、でも中には縮小しつつあるマイニングプールもあるだろうから、それがもしETCだったら・・・」という危険な仮説にそれなりの信憑性が加味されたからこそ、ターゲットにされたETC価格は-7%の下落に見舞われたともいえよう。微弱な何かがはらんでいると、すぐにつけ込む者が現れる。これが仮想通貨とブロックチェーンにおける今後の課題だろう。
■国連レベルで危険視されたハッカー国家
国連安全保障理事会が北朝鮮制裁の履行状況を調査する中で、北朝鮮があろうことか外貨獲得手段にサイバー攻撃を図り暗号通貨を不正取得してきた、と発表した。日本経済新聞が今年3月に報じている。
具体的には、北朝鮮が制裁を回避しながらも資金調達を進めるためにサイバー攻撃強化に奮闘しており、暗号通貨取引所への不正アクセスに成功したというものだ。その結果、2017年1月から2018年9月の短期間で555億円以上の資産を強奪したという。さらには、国内取引所コインチェックでの暗号通貨ネム(NEM/XEM)の巨額流失にも関与し、日本や韓国での仮想通貨交換業者に対して少なくとも5回の攻撃を成功させたとされている。
中央銀行を含めた金融機関をハッキングし、国内司法はもとより国際倫理の観点からも大スキャンダルと位置づけるべき事態だが、当の北朝鮮は涼しい顔で以前から500人規模のサイバー攻撃部隊を有していたとの報告もある。ブロックチェーン技術を含めた最先端技術を駆使しながら攻撃に邁進しているとの指摘もあるから驚きだ。アメリカ等が経済制裁を施しても、反省するくらいならハッキングして自国を潤わせてしまう国家であれば、経済制裁だけではなく真剣に「ハッカー軍団を相手に国際政治を交わしている」と肝に銘じて対策を再考すべきだろう。それはもちろん、狙われている日本の国民としても市民の平和を守るために立ち上げたLibertyとしても、一層厚みのある対策を講じることが今後の課題となっていくに違いない。